今回は、前回の記事「IT技術者が仕事中にADHDだと感じたら|心療内科受診までの実体験」でお話しした心療内科受診の続編として、実際にWAISテストを受けてワーキングメモリーの特性が判明し、具体的な対策を見つけるまでの体験談をお話しします。前回同様、同じような悩みを抱えるエンジニアや社会人の方にとって、少しでも参考になれば幸いです。
1. 前回記事のおさらい:心療内科受診まで
前回の記事では、仕事でのミスが続く日々から心療内科を受診するまでの経緯をお話ししました。上長からの指示の認識齟齬が頻発し、受けた指示に対して全く違うアウトプットを出してしまうことが続いたため、ADHDの可能性を疑い、専門医に相談することを決意しました。
心療内科での初診では、医師から「より詳しく調べるために、WAISテストを受けてみませんか?」と提案されました。今回は、その検査を実際に受けた体験と、結果から得られた気づきについてお話しします。
前回記事をまだお読みでない方へ
この記事は前回の「IT技術者が仕事中にADHDだと感じたら|心療内科受診までの実体験」の続編です。より詳しい背景を知りたい方は、ぜひ前回記事もご覧ください。
2. WAISテストとは?基本的な概要
ADHDの疑いを持った私は、より詳しく自分の特性を知るため、「WAIS(ウェイス)テスト」について調べました。正式名称は「Wechsler Adult Intelligence Scale」で、16歳以上の成人を対象とした知能検査です。
WAISテストの特徴
- 全般的な知的能力の測定: IQだけでなく、認知能力の詳細なプロフィールが分かる
- 4つの指標: 言語理解、知覚推理、ワーキングメモリー、処理速度を個別に評価
- 所要時間: 約60-90分程度
- 実施場所: 心療内科、精神科、心理相談室など
特にADHDの診断で重要な指標:
- ワーキングメモリー: 情報を一時的に保持・操作する能力
- 処理速度: 情報を素早く正確に処理する能力
WAISテストは単独でADHDの診断を行うものではありませんが、個人の認知的な特性を客観的に把握するための重要なツールとして活用されています。私の場合、自分の「苦手」が具体的にどの部分にあるのかを知りたいと思い、受検を決意しました。
3. 心療内科での受診体験
WAISテストを受けるため、私は地域の心療内科を受診しました。受診の流れは以下のような感じでした:
初診での流れ
- 問診: 現在の困りごと、過去の経歴、家族歴などを詳しく聞かれました
- 症状の整理: 仕事での具体的なミス例や、日常生活での困りごとを話しました
- 検査の説明: WAISテストの内容や目的について詳しく説明を受けました
- 予約: 別日にテスト実施の予約を取りました
医師に「WAISテストを受けたい」と希望を伝えたところ、快く対応していただけました。事前に症状や困りごとを整理してメモにまとめていったことで、スムーズに状況を伝えることができました。
検査当日
検査は心理士の方が担当してくださいました。様々な問題に取り組む中で、自分が得意な分野と苦手な分野がはっきりと分かれることを実感しました。言語的な理解は得意でしたが、数字を覚えて逆順に言う問題や、複数の情報を同時に処理する問題では明らかに苦戦しました。
4. 診断結果:ワーキングメモリーの特性が判明
結果説明の日、私は緊張と期待が入り混じった気持ちで病院を訪れました。検査結果は、私の予想通り、そして予想以上に明確なものでした。
私の検査結果(概要):
- 全体的なIQ:平均~平均より上
- 言語理解:平均~平均より上
- 知覚推理:平均~平均より上
- ワーキングメモリー:平均よりやや低め
- 処理速度:平均範囲内
特に注目すべきは、ワーキングメモリーの数値が他の指標と比べて明らかに低いことでした。医師からは「ワーキングメモリーが相対的に弱いことで、複数の情報を同時に処理したり、指示の詳細を保持したりすることが困難になっている可能性がある」という説明を受けました。
ワーキングメモリーとは
ワーキングメモリーは、簡単に言えば「脳の作業台」のようなものです。例えば、電話番号を聞いて、それを覚えながら電話をかける。または、複数の指示を受けて、それらを順序立てて実行する。こうした「一時的に情報を保持しながら、それを使って何かを処理する」能力がワーキングメモリーです。
私の場合、この「作業台」が一般的な人より少し小さいため、情報があふれやすく、大切な情報を落としてしまうことが多かったのです。
5. 診断後の気持ちの変化
検査結果を聞いた瞬間、私の中で大きな変化が起こりました。長年抱えていた「なぜ自分はこんなにミスが多いのか」という疑問に、ついに明確な答えが得られたのです。
診断前の感情
- 自己嫌悪: 「また同じミスをしてしまった」という自分への失望
- 不安: 「今度は大丈夫だろうか」という常時の緊張感
- 孤立感: 「なぜ自分だけがこんなにミスをするのか」という疎外感
- 無力感: 「努力しても改善しない」という諦めに近い気持ち
診断後の感情
- 安堵感: 「理由があったんだ」という納得
- 希望: 「対策を立てることができる」という前向きな気持ち
- 客観視: 「これは脳の特性であり、人格の問題ではない」という理解
- 受容: 「完璧でなくても、工夫すれば対応できる」という現実的な見方
特に印象的だったのは、長年の自己否定から解放された感覚でした。「怠慢だから」「注意力がないから」ではなく、「脳の情報処理の特性」として理解できるようになったことで、自分を責めることが大幅に減りました。
6. 実践している具体的な対策
ワーキングメモリーの特性を理解した後、私は具体的な対策を立て始めました。「脳の作業台が小さいなら、外部の道具を使って補えばいい」という発想で、様々な工夫を試しました。
主な対策方法
1. スマホのTodoリストアプリの活用
最も効果的だったのは、スマホのTodoリストアプリ(私は「Any.do」を使用)を活用することでした。
- 即座の記録: 指示を受けた瞬間にアプリに入力
- 定期的な確認: 1時間おきにアラームを設定し、リストを確認
- 詳細な分解: 大きなタスクを小さなステップに分けて記録
- 優先順位の明確化: 重要度に応じてタスクに色分けやラベルを設定
2. 会議での工夫
- 事前準備: 議題を事前に確認し、質問事項をメモ
- 録音許可: 重要な会議では録音させてもらい、後で詳細を確認
- 確認の習慣: 「つまり、○○ということですね?」と要点を復唱
3. 作業環境の整備
- シングルタスク: 一度に一つのことだけに集中
- チェックリスト: 定型作業用のチェックリストを作成・活用
- ダブルチェック: 重要な作業は必ず同僚に確認を依頼
Todoアプリ活用のコツ:
単にタスクを記録するだけでなく、「なぜそれをやるのか」「どんな結果が期待されているのか」も一緒にメモしています。これにより、タスクの途中で方向性を見失うことが大幅に減りました。
7. 現在の働き方と今後の展望
WAISテストを受けてから約1年が経ちましたが、仕事でのミスは確実に減少しています。完全になくなったわけではありませんが、以前のような「なぜミスをしたか分からない」状況は大幅に改善されました。
変化した点
- ミスの頻度: 月に数回あったミスが、月に1回程度に減少
- ミスの質: 重大なミスはほぼなくなり、軽微な見落とし程度
- ストレス: 「また間違えるかも」という不安が大幅に軽減
- 効率: 適切な対策により、作業効率が向上
職場での理解
直属の上司には診断結果について相談し、理解を得ることができました。「病気だから仕方ない」ではなく、「特性を理解して、より良い働き方を見つけよう」という前向きなサポートを受けています。
今後の目標
現在は、自分の特性を活かせる分野での専門性を高めたいと考えています。ワーキングメモリーは弱くても、論理的思考や創造性は平均以上であることが分かったので、設計や改善提案などの分野により力を入れていく予定です。
まとめ
前回の記事でお話しした心療内科受診から、WAISテストを通じて自分のワーキングメモリーの特性を知ったことで、長年の悩みに明確な答えが得られました。重要なのは、これが「治すべき病気」ではなく、「理解して付き合うべき特性」だということです。
この2回の体験から得た重要なポイント:
- 仕事でのミスには、個人の特性が関わっている場合がある
- 一人で悩まず、段階的に相談することが大切
- WAISテストは自己理解を深める有効なツール
- 特性を知ることで、効果的な対策を立てられる
- 完璧を目指すより、工夫して対応する方が現実的
- 専門医への相談は、思っているより気軽にできる
もし今、仕事でのミスや集中力の問題で悩んでいる方がいらっしゃったら、前回記事でお話しした「症状の記録」から始めて、段階的に専門家に相談することをお勧めします。自分の特性を客観的に理解することで、新しい解決策が見つかるかもしれません。
この記事が役に立ったと思ったら
同様の経験をお持ちの方や、ご質問がある方は、ぜひコメントでお聞かせください。また、SNSでのシェアも大歓迎です。一人でも多くの方に、自己理解の大切さが伝わることを願っています。
関連記事:「IT技術者が仕事中にADHDだと感じたら|心療内科受診までの実体験」もぜひご覧ください。
※この記事は個人の体験に基づいています。症状や対策には個人差があるため、気になる症状がある場合は専門医にご相談ください。

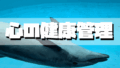

コメント