今回は、私自身がIT技術者として働く中で「もしかしてADHDかもしれない」と感じ、実際に心療内科を受診するまでの体験談をお話しします。同じような症状で悩んでいるIT技術者の方に、少しでも参考になれば幸いです。
※重要な注意事項
この記事は私個人の体験談であり、医学的なアドバイスではありません。症状や対処法は人それぞれ異なります。気になる症状がある場合は、必ず専門医にご相談ください。
仕事中に感じた違和感・症状
IT技術者として数年働く中で、「なんか他の人と違うかもしれない」と感じる場面が増えてきました。
具体的な症状
最も困ったのは以下のような症状でした:
依頼されたことが頭に入らない
- 上司や同僚から口頭で依頼を受けても、すぐに内容が曖昧になってしまう
- 「確かに聞いたはずなのに、何を言われたか思い出せない」という状況が頻発
メールの指示を読み飛ばしてしまう
- 重要なメールでも、3つの指示があるうちの1つしか指示と認識できなかった
- 後から「なぜこれを見逃したんだろう」と自己嫌悪に陥る
認識齟齬の発生
- 同じ話を聞いても、他のメンバーと理解が異なることがある
- 記録を確認しても「言われた記憶がない」ということが起きる
これらの症状により、仕事でのミスが増え、チーム内での信頼関係にも影響が出始めていました。
一人で悩んでいた時期
最初は「集中力が足りないだけ」「仕事に慣れていないから」と自分を責めていました。
自分なりの対処を試みる
- より細かくメモを取る
- タスク管理ツールを導入する
- 睡眠時間を増やす
- カフェインを控える
しかし、どんな対策を講じても根本的な改善には至りませんでした。「自分はIT技術者に向いていないのかもしれない」とさえ思うようになりました。
相談を決意したきっかけ
転機となったのは、ある日のプロジェクトでの出来事でした。事前に行った認識合わせを行い、それに従って成果物を出したが、依頼者の意図が全く入っておらず、認識齟齬があったことが判明。チーム全体に迷惑をかけてしまいました。
その夜、妻に「最近、仕事でミスが多くて辛い。このままだとチームに迷惑をかけ続けてしまう」と打ち明けました。すると妻からは「つらかったらその現場退場すればいいじゃない。上司もわかってくれるよ。」と言ってもらい、気持ち的に楽になりました。
冷静になって俯瞰的に起きている事を判断してみると、これらの症状には何かしらの原因があるはずだと考えるようになりました。エンジニアとして普段からシステムの障害対応を行っている経験を活かし、自分自身がADHDではないかと疑い、そこに向けて切り分けを行うことにしました。
症状の記録と整理方法
相談に向けて、まずは症状を客観的に記録することから始めました。
記録項目
以下の項目を日々記録しました:
日時・状況
- いつ、どのような場面で症状が発生したか
- 会議中、メール確認時、タスク実行時など
具体的な症状
- どのような困りごとが発生したか
- 自分なりの対処をしたか
- 結果としてどうなったか
影響度
- 仕事への影響(大・中・小)
- チームへの影響の有無
- 自分の精神的な負担度
記録ツール
- Google スプレッドシート:日付、症状、影響度を表形式で管理
- スマホのメモアプリ:気づいた時にすぐ記録
- 業務日報:既存の業務記録と症状記録を関連付け
2週間ほど記録を続けると、パターンが見えてきました。特に、複数の情報を同時に処理する場面で困りごとが発生しやすいことが分かりました。
相談先と相談内容
記録を基に、段階的に相談を進めました。
相談先の整理表
| 相談先 | 相談内容 | 期待する回答・支援 | 相談結果 |
|---|---|---|---|
| 配偶者(妻) | 症状への不安、仕事への影響 | 精神的なサポート、客観的な意見 | 「つらかったらその現場退場すればいいじゃない。上司もわかってくれるよ。」と言ってもらい、気持ち的に楽になった |
| 直属の上司 | 業務での困りごと、改善方法 | 業務調整、理解・配慮 | 「どうしてもつらかったら異動できるように配慮する」 |
| 心療内科医師 | 症状の医学的評価、検査の必要性 | 専門的な診断、治療方針 | 詳細な検査の提案と臨床心理士への紹介 |
| 臨床心理士 | 心理検査の実施、結果の解釈 | 客観的な能力評価、特性の把握 | WAIS-IV検査実施と詳細な結果説明 |
実際の相談プロセス
1. 妻への相談
つらい気持ちを素直に伝えました。「一人で抱え込まないで」という言葉に救われました。
2. 上司への相談
「最近、業務でミスが多く、原因を調べたいと思っています」と切り出しました。記録した症状を見せながら説明すると、理解を示してくれました。
3. 心療内科への相談
事前に電話で症状を説明し、受診の予約を取りました。初診では、記録した症状一覧を持参しました。
心療内科受診の準備と流れ
受診前の準備
必要書類・持参物
- 健康保険証
- お薬手帳(服用中の薬がある場合)
- 症状記録(2週間分)
- 質問リスト(聞きたいことを事前にまとめ)
質問リストの例
- これらの症状はADHDの可能性があるか?
- 検査にはどのようなものがあるか?
- 検査費用や期間はどの程度か?
- 仕事を続けながら治療できるか?
受診当日の流れ
初診(約1時間)
- 問診票の記入(30分)
- 医師との面談(30分)
- 症状の詳細確認
- 生育歴の聞き取り
- 日常生活への影響度確認
検査の提案
医師から「より詳しく調べるために、臨床心理士による心理検査を受けてみませんか?」と提案されました。
検査日程の調整
- WAIS-IV(知能検査):約2-3時間、臨床心理士が実施
- その他必要に応じた検査
- 結果説明:検査から1-2週間後、臨床心理士より
検査結果と得られた安心感
検査結果の概要
WAIS-IVの結果、以下のことが分かりました:
得意な分野
- 言語理解:平均より高い
- 知覚推理:平均より高い
苦手な分野
- ワーキングメモリー:若干低め
- 処理速度:若干低め
臨床心理士からの説明
「ADHDと診断するほどの症状ではありませんが、ワーキングメモリーと処理速度が他の能力に比べて相対的に低いことが、お困りの症状につながっている可能性があります」
この説明を聞いて、大きな安心感を得ることができました。
エンジニア思考での理解
システムに例えて考えると:
- CPU性能(言語理解・知覚推理):高性能
- メモリ容量(ワーキングメモリー):やや不足気味
- ディスクI/O速度(処理速度):やや低速
つまり、「故障」ではなく「スペックの特性」だと理解できました。サーバーでも、メモリ不足やI/O性能不足の場合は適切な対策を講じるように、自分の特性に合わせた対策を考えればよいのです。
エンジニア思考で自分を理解する
問題解決のアプローチ
1. 現象の把握
- 症状の記録と分析
- 発生条件の特定
2. 原因の究明
- 専門家(医師・臨床心理士)への相談
- 科学的な検査による検証
3. 対策の実装
- 検査結果に基づいた対処法の検討
- PDCAサイクルでの改善
このプロセスは、まさに普段仕事で行っている障害対応と同じでした。
得られた対策
検査結果を基に、以下の対策を実装しました:
ワーキングメモリー不足への対策
- 重要な情報は必ずメモを取る
- 複数タスクの同時実行を避ける
- チェックリストを活用する
処理速度の低さへの対策
- 時間に余裕を持ったスケジューリング
- 集中できる環境作り
- 定期的な休憩の確保
同じような悩みを持つ方へのメッセージ
一人で抱え込まないで
私の体験を通じて最も伝えたいのは、「一人で悩み続けないでほしい」ということです。
エンジニアは問題解決が得意な職種ですが、自分自身の問題については客観視が難しいものです。信頼できる人に相談することで、新しい視点や解決策が見つかる可能性があります。
原因がわかることの安心感
「なぜこんなミスをしてしまうのか」という謎が解けることで、大きな安心感を得られました。原因が分からない不具合ほど怖いものはありません。検査により自分の特性を客観的に把握できたことで、適切な対策を考えられるようになりました。
相談・受診のハードルを下げて
心療内科と聞くと身構えてしまう方もいるかもしれませんが、実際は思っているより気軽に相談できる場所でした。風邪で内科を受診するのと同じような感覚で、メンタルヘルスについても専門家に相談してよいのです。
まとめ:私が実際に行った行動
ステップ1:症状の記録(2週間)
- スプレッドシートで症状を記録
- 発生パターンの分析
- 影響度の評価
ステップ2:段階的な相談(1ヶ月)
- 配偶者への相談と精神的サポート
- 上司への状況報告と理解を得る
- 人事担当への制度確認
ステップ3:専門医への相談と検査(2週間)
- 心療内科の予約と受診
- 詳細な問診と臨床心理士による検査の実施
- 結果に基づく対策の検討
ステップ4:継続的な改善
- 検査結果を基にした業務方法の改善
- 定期的な振り返りと調整
著者からの一言
この記事を書くまでには長い道のりがありました。最初は「自分だけの問題」だと思い込んでいましたが、実際に相談してみると多くの人が理解を示してくれました。
IT業界には、集中力や注意力に関して悩みを抱えている方が少なくないと感じています。しかし、適切なサポートや対策により、必ずしも転職や退職を考える必要はないということも実感しました。
もしこの記事を読んで「自分にも当てはまるかもしれない」と感じた方がいらっしゃいましたら、一人で悩まずに信頼できる人に相談してみてください。私の体験が少しでも参考になれば幸いです。
繰り返しになりますが、この記事は私個人の体験談です。症状や対処法、検査結果は人それぞれ異なります。気になる症状がある場合は、必ず専門医にご相談ください。
関連記事として、IT技術者のメンタルヘルス管理についても書いています。
この記事が役に立ったと感じたら、コメントやSNSでのシェアをお願いします。同じような悩みを持つ方に届けば嬉しいです。

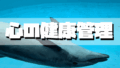
コメント