今回は私自身がインフラエンジニアとして現場で経験した適応障害について、そしてそこから学んだことを率直にお伝えします。特に同じような職種で働く方々に向けて、「自分を大切にする」という当たり前だけれど実践が難しいことについて考えていきたいと思います。
適応障害の兆候 – 自分自身の変化に気づくこと
最初は誰でも気づきにくいものです。私の場合、気持ちが非常に落ち込む、朝起きるのが異常に辛い、単純なミスが増えていくといった症状が日に日に強くなっていきました。
特にインフラエンジニアの仕事は、システムの安定運用に対する責任感や、障害対応の緊急性など、常に緊張感を強いられる環境にあります。自分の場合、そのプレッシャーが日々積み重なっていくと、ある日突然、心が折れて仕事のパフォーマンスが著しく落ちてしまいました。
見落としがちな心のSOSサイン
- 些細なミスが連発するようになった
- チャットやメールの通知音に過剰に反応する
- 指示された内容がすっぽり抜け落ちることがある
- 質問されたとき、通常なら回答できるのに、頭が真っ白になってしまう
これらは私が経験した症状ですが、適応障害は人によって現れ方が異なります。ただし共通しているのは、「いつもの自分」ではなくなっているということです。その変化に早く気づくことが、第一歩となります。
上長からのプレッシャーとどう向き合うか
IT業界、特にインフラ部門では納期やシステム安定性に対する要求が厳しく、上長からのプレッシャーは避けられないものです。私の場合、「あなたのキャリアならもっとできるはずだ」という言葉が心に深く刺さっていきました。
上長とのコミュニケーションで大切なこと
上長からのプレッシャーを感じた時、多くの人は「もっと頑張らなければ」と自分を追い込みがちです。しかし、それは解決策ではありません。むしろ状況を悪化させる可能性が高いのです。
大切なのは、自分の状態を正直に伝えることです。「このタスクについては時間がかかりそうです」「この部分は不安があるので、サポートをいただけますか」といった形で、早めに相談することが重要です。完璧を求めすぎず、必要な時には助けを求める勇気を持ちましょう。
心療内科への一歩 – 踏み出すことの大切さ
「心療内科に行く」という選択肢を考えたとき、私は長い間躊躇していました。「そこまでではない」「自分で何とかできるはず」という思いが強かったからです。しかし、今振り返ると、もっと早く専門家に相談するべきだったと感じています。
心療内科への受診は決して恥ずべきことではありません。むしろ、自分自身を大切にする勇気ある選択です。職場で心が折れた時、専門家のサポートを受けることで、客観的な視点と適切な対処法を得ることができます。
最初の受診は確かに勇気がいりますが、その一歩を踏み出すことで状況が大きく変わる可能性があります。私の場合、受診して適応障害と診断されたことで、「これは治療が必要な状態なんだ」という認識を持つことができました。
ここで大事なのは、正しい診断を受けるために、自分を取り繕うのではなく正直にありのままを伝えることが重要です。心療内科の医師はあなたの味方です。今、置かれている自分の立場と気になる症状を正直に伝えましょう。
診断書の効力 – 休養を正当化するために
適応障害と診断された場合、医師から診断書を発行してもらうことができます。この診断書は、会社で休職を申請する際の重要な根拠となります。
多くのエンジニアは「チームに迷惑をかけてしまう」「休むと評価が下がる」という不安から、無理を続けてしまいがちです。しかし、診断書があれば、あなたの休養は医学的に必要なものとして認められます。会社の制度によっては傷病手当金なども受けられる可能性があります。
私の経験では、診断書を提出して休職したことで、周囲の目を気にせず心身を回復させる時間を確保することができました。
回復への道のり – 薬物療法と心の整理
適応障害の治療では、度合いによって薬を処方してくれます。私の場合は、気持ちを落ち着かせる薬を医師に処方してもらい、それを服用することで、精神的に落ち込む回数が劇的に減りました。
特に記憶に残っているのは、薬を飲み始めてから「頭が真っ白になる」という症状が軽減されたことです。以前は上長からの質問に対して思考が凍結してしまう状態でしたが、薬物療法によって少しずつ落ち着いて考えられるようになりました。
ただし、薬はあくまでも回復を助けるツールの一つです。それと並行して、自分自身の働き方や価値観を見つめ直す時間を持つことも重要でした。
職場復帰に向けて – 自分のペースを大切に
適応障害からの回復には個人差があります。数週間で復帰できる人もいれば、数ヶ月、あるいはそれ以上の時間が必要な場合もあります。大切なのは、他人のペースではなく、自分自身の回復状況に合わせることです。
私は最初の1か月は完全休養し、1か月の待機期間を経て約2ヶ月で職場復帰しました。この2か月という時間は自分にとってとても有意義なもので、心の病を癒すにはとても良い期間でした。
この間、最初の1週間はひたすら起きてご飯を食べては寝ての生活でしたが、その次の週から自分の興味のある事やまとまった時間が取れないと取り組めなかったことを行う事で自分を取り戻していくのを徐々に感じていました。
まとめ – 自分の身体と心が何よりも大切
インフラエンジニアとして、システムの安定稼働を支える責任感から、つい自分自身を後回しにしがちです。しかし、どんな重要なシステムよりも、あなた自身の心と身体の方が大切です。システムには代替手段や復旧策がありますが、あなたの人生は一つしかありません。
適応障害を経験した今、私が最も伝えたいのは以下の点です:
- 心身の変化に敏感になり、早めに対処する
- 無理をせず、必要な時には専門家の助けを求める
- 診断書を活用し、必要な休養を取る権利を行使する
- 回復には時間がかかることを認め、焦らない
- 復帰後も自分を大切にする働き方を継続する
もし今、あなたが「何かがおかしい」と感じているなら、それは大切なサインです。そのサインを無視せず、早めの対処を検討してください。そして何より、「自分の健康が最優先」という当たり前のことを、当たり前に実践できる勇気を持ちましょう。
著者からの一言
この記事を読んでいるあなたへ。私も同じインフラエンジニアとして、日々の業務の大変さを知っています。夜中の障害対応、難しい技術課題、厳しい納期…それらは確かに重要です。しかし、それ以上に大切なのはあなた自身です。
私は適応障害になって初めて、「無理をしないこと」の本当の意味を理解しました。それまでは口では「無理しないように」と言いながらも、実際は常に限界ギリギリで働いていました。今では「これ以上は無理」というラインを見極め、そこで立ち止まる勇気を持てるようになりました。
あなたにも、自分を大切にする選択をしてほしいと心から願っています。
※この記事は個人の経験に基づくものであり、症状や対処法には個人差があります。心身の不調を感じた場合は、必ず医療機関での受診をお勧めします。


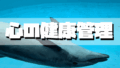
コメント